Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ
INTERVIEW
2021.11.25

Panorama Panama Town、<好き>の正体に手を伸ばす最新ミニアルバム「Faces」

「なんでこんなに話してるの?」っていうぐらい近くなったメンバーとの距離
ー話が遡りますけど、2020年2月にドラムの(田村)夢希くんが脱退してからは3人で活動していますね。当初は困惑することも多かったですか?
岩渕:いや、サポートで大見(勇人)っていう大学の友だちが入ってくれて。軽音(学部)で何回も一緒にコピーをやってたんですよ。そいつが僕のポリープ手術の休養が終わってからすぐに一緒にスタジオに入ってくれたんですけど、そのスタジオがおもろかったんです。
ー「おもろい」とは、どういう意味で?
岩渕:めっちゃ新鮮だったんです。当たり前ですけど、いままで他のドラマーがパノパナに入ることもなかったから。大見とスタジオに入ってる時間がすごく楽しくて。新しいバンドを組んでるような気持ちでしたね。サポートだけど、「一緒にいいものを作っていくぞ」っていう感じなんです。
ー他のドラマーを試したりせず、すぐに大見くんと「一緒にやれそうだ」ってなったんですね。
岩渕:そう。それがデカいかもしれない。揺らぐ時間がなかったので。

ー浪越くんはどうですか? 3人の活動になって変わったことはありますか?
浪越:メンバーの距離がすごく近くなりましたね。
岩渕:タノとも、より音楽とかバンドの話を詳しくできるようになって。
ーその変化はコロナが重なったことも大きいですか?
浪越:コロナ禍で会えなかったぶん言いたいことが溜まってたのはあるかもしれないです。「僕はもっとこうしたい」みたいなのが強くなってて。会ったときはめっちゃ話す、みたいな。
岩渕:たしかに。いまは「なんでこんなに話してんの?」って感じだもんね(笑)。
タノ:風通しが良くなった気がしますね。それはコロナだけじゃなくて、(岩渕のポリープ手術で)1回止まったのもデカかったのかなと思ってるんですよ。もうそんなに安々と止まったりしたくない、って気持ちを入れ替えるきっかけになった気がします。
岩渕:いまは思ってることがあったら言うし、相談があったらすぐ言うしね。とにかく音楽の話をする時間がめちゃくちゃ増えました。こういう曲があったらいいよね、っていうのを日常会話レベルでするから。そこが全然いままでとは違うなって。
タノ:あの新譜がよかった、とかね。
岩渕:そうすると、アルバムを作るときに「あの感じ」って言っただけで全員知ってる、みたいな状況になるから、すごく話が早いんですよ。
ー特にいまバンドのなかでハマってる音楽はありますか?
岩渕:サウスロンドンのバンドシーンはハマってるというか、ずっと聴いてるよね。
タノ:うん、今回の制作のときはそうですね。
岩渕:あとは結局ストロークス。(同じ時期の)アークティック(モンキーズ)とか、フランツ(フェルディナンド)よりも、ストロークス一択っていう感じですね。
ーそう言えば、8月に「パノパナの日」のライブを見させてもらいましたけど、浪越くんと岩渕くんでストロークスのカバーをやってましたよね。
浪越:あ、あの恥ずかしいやつを見られてたんですね(笑)。
ーいや、良かったですよ(笑)。パノパナって昔のインタビューでも、「ストロークスが好き」ってずっと言ってたけど、いまはよりその気持ちが強くなっているんだろうなと思いました。
岩渕:たしかに自分の「好き」をより深堀りしてる感じはありますね。大学時代から好きだったものに対して、そこ以外には行かず、とにかくちゃんと掘っていく、みたいな。
ーいまなら、どうしてストロークスが好きなのかも言葉にできるんですか?
岩渕:ミニマリズムだと思いますね。なんて言うんだろうな、洗練されてるんだけど、必要なものは全部鳴ってる感じ。あとは引きの美学というか。めちゃめちゃ熱いけど、その熱さが全部5人のなかにある。外に「聴いてー!」っていう感じじゃない。そこがめっちゃいいなと思ってます。
バンドの転換点になった『Rolling』を経て、新作『Faces』へ
ーそれってそのままパノパナのいまのモードのヒントになってますよね。今年4月に出した『Rolling』の以降の楽曲は、特にそういう方向になっていて。
岩渕:『Rolling』は、メンバーが抜けてから、2020年の1年間でやってきたことをいったん詰め込みました、みたいなEPなんですね。新しい名刺代わりというか。あの頃は今作(『Faces』)に比べると、まだ幅広かったんですよ。そこからどんどん狭くしてった感じですよね、今回は。
ーなるほど。
浪越:たとえば、(『Rolling』に収録の)「Sad Good Night」に関しては、この方向で突き詰めていきたいけど、もっと洗練させていきたいと思ったし、「氾濫」とか「Rodeo」は、もっと力まなくてもかっこいいなと思ったんですね。そういう意味で、『Rolling』は次に進むために必要だったんです。
岩渕:特に「Sad Good Night」は、音を減らしていくっていうところをすごく考えてました。これは浪越とけっこう話したんですけど、ベースがルートでコード感を出して、ギターが違うところにいってても、全体でコードになっていればいいんじゃないか、とか。それが今回の作品で言うと、「Strange Days」とか「Melody Lane」に出たかなと思います。
ーその2曲は、ドラマ『ギヴン』に書き下ろした楽曲ですね。特に「Strange Days」のほうは青春っぽさが滲み出た楽曲で。『Rolling』に続き、石毛輝さんのプロデュースになります。
岩渕:石毛さんは、2016年に『PROPOSE』っていうインディーズのアルバムを出したときにlovefilmとツーマンをさせてもらったんですよ。そこからずっと交流はあって。音源が出るたびに聴いてもらってたんです。そんななかで(前作の)「Rodeo」のデモMVを作ってたときに、石毛さんが反応してくれて。「かっこええやんか」みたいな。「自分だったら、こうしたい」みたいなのを言ってくれたところから、ふたりで1回飲みに行って。その流れですかね。
ー「Strange Days」は、石毛さんとどんなふうに膨らませていったんですか?
岩渕:自分で作ったデモから、3人である程度のデモを作っていって、それを石毛さんとブラッシュアップしてって感じですね。石毛さんの家に行って。
浪越:『Rolling』で4曲を一緒にやったときに、本当に石毛さんがスゴいなと思ったんですよ。音の差し引きとか、展開のつけ方とか。めちゃくちゃ感動したんです。それでわかったことがたくさんあったから、「Strange Days」は、岩渕と一緒にデモを作っていく段階から、ほぼほぼ自分たちのなかで完成してたんです。それを石毛さんと一緒にやることで再確認したというか。
ータノくんは?
タノ:この曲はドラムの音色がキーになるなと思ってて。打ち込みの音を探す時間が長かったですね。そのときに、石毛さんの言ったことで印象に残ってるのが、「運任せて試して、こういう音がいいじゃなくて、明確にどういう音か、ちゃんと説明できるようにならないと」みたいな。そういうのを作れるようにならないといけないっていうのが、ほんまそのとおりだなと思いました。
浪越:石毛さんは、バンドとしてどういう音楽をやっていきたいのかっていうことをすごく大事にしてるんですよ。こういうバンドだったら、こういう音を出すだろうっていうこと。そういう視点で、僕らはパノパナだから、こういうアレンジになるっていうのを教えてくれましたね。
ーもう1曲、ドラマ『ギヴン』に書き下ろした「Melody Lane」のほうは、もともと劇中のバンドthe seasonsが演奏する曲として作ったものです。
岩渕:ドラマで高校生が演奏するっていうのは外せなかったですね。自分たちも19歳からバンドをやってるから、そのときの衝動を曲作りにおいてプッシュして作っていきました。
タノ:プレイスタイルとして、そのキャラクターがやりそうなことをやってるんですよ。
岩渕:各々が原作のキャラがやりそうなフレーズを入れてくるっていう。あんまりそういう注文はなかったんですけど(笑)。
タノ:もともとはセルフカバーをする予定もなく作ってたんです。
ー劇中のバージョンとセルフカバーでは、同じ曲なのにかなり印象が変わりましたよね。アレンジをするうえで意識したことはありましたか?
岩渕:アレンジは手こずりましたね。ここまで歌をフィーチャーした曲は今回のアルバムではなかったので。『Faces』のテーマとして、あんまりコードをジャーンって弾かないっていうのがあって。「Melody Lane」は弾き語りで作ったから、とことんコードを弾く曲だったので、そこからコードのない曲にしていくっていう過程が大変だったんです。

岩渕:ロシアのポストパンクとかもめっちゃおもろくてね。そればっかり聴いてたんです。
浪越:たしか「Strange Days」を作ったあとにそっちを発見したんですよ。もしかして、こういうのに共鳴できるかな、みたいなのがあって。
岩渕:自分たちって別にキュアーとかはジャストな世代じゃないけど、ドラムスとかがリヴァイバルしたときにはジャストで聴いてるんです。そのドラムスの流れが終わったのかと思ってたら、ロシアとかで再熱してたんですよ。
浪越:あっちでは話題になってたりね。
岩渕:そう、まだやってるやつらがいた。それがいまの自分らにも合うなと思ったんです。僕らは大学のときにドラムスもコピーしてたので。その共鳴感みたいなのはめっちゃありましたね。いまサウスロンドンでは、もう1回ジョイ・ディヴィジョンをやってるバンドがいっぱいいたり。
ー要するに、00年代のロックンロール・リバイバルってめちゃくちゃ流行ったけど、いまもそれをやり続けてるバンドが世界中にいることが刺激になったと。
岩渕:うん。いまヒップホップを聴いて、「バンドでこれをやったらおもしろいのにな」って思ったり、昔の音楽を引用する感じは、どの国もある程度は一緒なんじゃないかなと思いますね。アイドルズっていうバンドがギャング・オブ・フォーのカバーをしてるのも、いまギャング・オブ・フォーをおもしろいと思ってるってことじゃないですか。それは万国共通にあるおもしろさなんじゃないかなと思うんです。それを自分らも思ってて。ああいうスカスカで踊れる曲って、ローが鳴ってるものとかトラップが流行ったあとに聴くと、おもしろいんですよね。
ナチュラルに高揚していく音像を目指して
ーいまの話を聴いて、今回のアルバムがすごく洋楽っぽいのも納得しました。たとえば、2019年の『GINGAKEI』とか『情熱とユーモア』みたいな作品が持っていたドメスティックなキャッチーさ、インパクトの強さとは距離を置いてるように思ったんです。
岩渕:無理をしなくなりましたよね。いまは自分らの肌に合うところをとことん考えるので。
タノ:薄まってしまうことに気づいたんですよ。アレンジなりでいろいろなものを詰め込みすぎると、ブレてしまうというか。

浪越:それ、すごいわかる。僕、ギターソロを弾くのが恥ずかしいなって思うことがあるんですよ。でも今回のギターソロって、ソロでっていうよりは全員でって感じなんですよね。
ー「100yen coffee」とか「Algorithm」は「Faceless」はまさにそうですよね。
タノ:いままでだったら、ギターが出るときは自分のベースはルート弾きすることが多かったんですけど、今回のソロってすごいおもしろくて。「Kingʼs Eyes」とかもそうですけど、曲全体で動かしていきながら、少しずつ場面の容量が増す感じがするんですよね。
岩渕:ここだけじゃないところにいけるようなね。
タノ:それがずっと地続きなんです。無理してあがってないけど、ふわっとあがる瞬間がある。
岩渕:たしかに。自分のデモでいけるところまでいって無理になったら、浪越の展開が入ってくる、みたいな。その曲のキーになる展開を作ってるのが浪越だったりすることが多くて。そのブリッジが気持ちいいからイントロに持ってこようとか。それが効いてる気がします。
ー気がついたらあがる感じを強く感じたのは「Algorithm」でした。基本的に渋めのギターがループしてるけど、気づいたらエモーショナルになっていて。
岩渕:これは早めにできた曲ですね。『Rolling』の「Sad Good Night」の延長が「Strange Days」だとしたら、「Rodeo」「氾濫」の延長って何なんだろう?みたいなことを考えてるときにできた曲です。ずっとツーコードで押し切って。
タノ:いままでだったら、「Algorithm」みたいな曲って分厚くやってたんですよね。そこを減らして減らして、かっこいいじゃんって思えたのは大きかったです。僕の全部のアレンジに共通するんですけど、極力ループに努めつつ、1ヵ所だけ外れてるんですよ。ずっと繰り返しに徹してると、どこかではずれたくなる。そこは正解なんじゃないかっていうのがあって。「100yen coffee」なんかも、コードから外れていくことで不穏なものがあったりして。そこが気持ちいいんですよね。
ー「Kingʼs Eyes」にはギターソロにホーンっぽい音を重ねてますよね。
タノ:あれは生です。
岩渕:3本吹いてもらってます。
ー着想のきっかけは何かあったんですか?
浪越:あれはブラック・ミディっていうバンドが、僕ら最近すごく好きで。かっこいいギターリフに何かしらの管楽器を使ったセクションを入れてるのがかっこいいよなっていう話をしてたところから、(ディレクターから)提案があったんですよ。
タノ:もともとのギターリフがシンセリフっぽかったんですよね。ロンドンっぽさがあるなって。だから相性はいいし。
岩渕:それが最後にしか出てこないっていうのがおもしろいですよね(笑)。
「Seagull Weather」はバンドの歌でもある
ーアルバムのなかで少し方向性が違うのが「Seagull Weather」ですね。爽やかで、シーサイドっぽい雰囲気が漂っていて。
岩渕:「Seagull Weather」はほとんどデモが出揃ってきたところで最後に息抜きみたいな感じで選びました。最初は、いい曲だけど、アルバムに入れるのは違うかなと思ってたんですけど。誰が押してたんやったっけ?
タノ:僕かな。こういうメロウな部分も自分らのなかのひとつとしてあるんですよ。だから『Faces』っていう作品として考えたときに、あったほうがいいんじゃないなと思ったんです。これは岩渕からトーキング・ヘッズがリファレンスだっていうのをもらってて。ちょうど『アメリカン・ユートピア』を聴いたあとで、トーキング・ヘッズのティナ・ウェイマス っていうベーシストがすごいなと思ってて。そういうグルーヴを目指しています。
岩渕:この曲があることで肩肘を張らなくていい感じがするんですよ。歌詞もすごく素直なので。
ー景色が目に浮かぶようなラフな言葉選びですよね。
岩渕:これ、あんまり話してないんですけど、バンドの話でもあるんですよ。
ーえ、そうなんですか? ラブソングかなと思って聴いてました。
岩渕:そう、ラブソングなんです。だから、バンドの曲って言いすぎると、あれなんですよね(笑)。言い方が難しいんですけど、いまの自分のいちばん裸な曲だと思います。

ー「Seagull Weather」って日本語で言うと......。
岩渕:かもめ日和みたいなことかな。全然なんの意味もないです。リフを弾いたときに、かもめっぽいなと思って。そのまま仮タイトルでいいやって決めたので。
ーいままでそういうタイトルのつけ方ってないですよね?
岩渕:音からっていうのはないですよね。『Faces』も意味がないですし。
ーいやいや、『Faces』に意味はあるでしょう(笑)。「Faceless」っていう曲からつながったものだとも思いますし。
岩渕:あはは、ま、そうですね。
「もっと人として話したい、君と」
ー「Faceless」はどんな曲にしようと思ったんですか?
岩渕:いちばんヤバい曲を作ろうと思ったんですよ。あんまり何も考えずに曲を作ってたデモがあって、それを気に入ってたんです。気持ち悪いですけど、いいな、みたいな。ただ、ちょっとかっこよすぎるから途中までアルバムに入れない可能性もあったんですけど、このぐらいエッジが立った曲があったほうがいいアルバムになるっていうことがわかってきて。それから、ちゃんとアレンジして、浪越のアイディアでブリッジミュートを合わせる展開が入っていったんです。
タノ:みんなバラバラ。でも噛み合ってる、みたいな曲ですね。
ーこれ、個人的にはパノパナの初期曲っぽいなと思いました。
浪越:「Faces」は、いまの「MOMO」をやろうと思ったんですよ。「Kingʼs Eyes」がいまの「シェルター」のつもりですね。個人的には。
岩渕:そんなこと思ってたんや(笑)。
ー結局、自分たちの「好き」を突き詰めていくと、初期っぽさに還っていく側面もあると思うんですけど、それって実は似て非なるものじゃないですか。自分たちではどう捉えていますか?
岩渕:今回やってて思ったのは、初期の頃に「これが好きだったんだろうな」とか、「なんで、これを作ったんだろう?」っていう理由を探していたようなところがあったんですよね。
浪越:「MOMO」を言語化したのが「Faces」だし、「パン屋の帰り」を言語化が「Melody Lane」だし。
岩渕:「世界最後になる歌は」みたいなリフを言語化して、「Strange Days」のアイディアにしたっていう発見もあったしね。「過去に戻ろう」感はないけど、そうなっていった感じかな。
タノ:なんとなく好きでやってたものが、いまはちゃんとわかるようになってるんですよ。音楽を広く聴くようになったし、自分のなかで噛み砕けるようになったので。こうやったら、ある程度こうなるっていうのもわかってきた。だから何も意識してないんです。洋楽っぽくとか、初期っぽくとか、日本向けじゃないとかも実際思ってなくて。作りたいように作ったら、こうなるよねって感じですかね。
ーなるほど。「Faceless」の歌詞は、この時代だからこそのテーマですね。顔を合わせなくても生きていけてしまう世の中だから出てきた言葉なのかなと思いました。
岩渕:いまは顔のない時代だなと思ってるんですよ。イメージで判別されることが増えてるなって。ライブハウスが感染を広げてるっていう話だったり、バンドマンはこうだとか、若い世代は、とか。しょうがない面もあるけど、冷たい時代だなって。そういうときに大事なのは顔だと思ったんです。人にはそれぞれの顔があって、違う生活があって、違う人生があって。バンドのなかにも4つの顔があるし。そこが失われてるっていうのが「Faceless」で歌いたかったことですね。もっと人として話したい、君とっていうのがすごくあったんです。

ーこういうメッセージ性のある歌詞に関しても、肩肘をはらなくなったところはありますか?
岩渕:ああ、そうですね。いまは「全員そうなってほしい」じゃなくて、「俺はこう思うよ」っていうか。疑問符になればいいのかなって思うようになってるから。
ーえ、いままでは全員そうなってほしいと思ってたの?
岩渕:.........思ってました(笑)。
一同:あははは!
タノ:啓蒙スタイル(笑)!
岩渕:「おかしいよ!」って言いたかったんですよ。でも、そういう伝え方だけじゃないなって。もっと疑問符をポンと打つぐらいの感じのほうがいまは伝わるんじゃないかと思ってます。
ー浪越くん、タノくんも、ソングライターの変化は感じていますか?
浪越:いま言ってた通りだと思います。『GINGAKEI』とか『Hello Chaos!!!!』って、タイトルにも表れてたとおり、「それぞれが違う」っていうメッセージをずっと歌い続けてるなって思ってて。いまもそのメッセージは変わってないけど、表現の仕方は変わったなと思いますね。
ーパノパナってデビューが早かったし、大学生のときから注目されてきたから、いま振り返ると、自分たちの魅力に無自覚に試行錯誤してきたところが多かったと思うんです。そこに自覚的になったことで、これからバンドは新しいフェーズに向かっていくのかなと思います。
岩渕:そこはあるかもしれないですね。『Hello Chaos!!!!』ではポップにやってみようとか、『PANORAMADDICTION』ではロックにやってみようとか、いろいろ試してますから。今回こういう作品を作ってみて思ったのは、いまだに自分は、自分たちの初期の曲のファンなんですよ。それを「なんで好きだったんだろう?」って考えていく。いまはそういうときですね。
取材・文:秦理絵
写真:今井駿介
サイン入りチェキプレゼント

Panorama Panama Town Mini Album『Faces』のリリースを記念して、SENSAのTwitterとInstagramにてプレゼント企画を実施!
アカウントをフォロー&RT、もしくはフォロー&「いいね」で、Panorama Panama Townサイン入りチェキを抽選で2名様にプレゼント!
詳細は下記の応募方法をご確認ください。
■応募方法
Twitterアカウントをフォローの上、以下のツイートをリツイート
【 #プレゼント 】
— SENSA (@sensajp) November 25, 2021
Panorama Panama Town Mini Album『Faces』のリリースを記念して、プレゼント企画を実施中!
本アカウントをフォロー&このツイートをRTで、サイン入りチェキを抽選で2名様にプレゼント!
抽選応募締切は12月3日(金)23:59まで!
詳細はこちら
https://t.co/28JvPzIGGF pic.twitter.com/nDIFXThkry
Instagramアカウントをフォローの上、以下のポストを「いいね」
■期間
2021年11月25日(木)19:00〜2021年12月3日(金)23:59まで
■当選発表
2021年12月8日(水)予定
■注意事項
※アカウントが非公開の投稿は応募を無効とさせて頂きます。
※当選者にのみDMもしくはメッセージでご連絡します。DM・メッセージの受信機能を有効にして頂くようお願い致します。
※当選のご連絡から2日以内にお返事がない場合は当選を無効とさせて頂きます。
※選考経過および結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。
※プレゼントの当選権利は、当選者本人に限ります。第三者への譲渡・転売・質入などはできません。
RELEASE INFORMATION
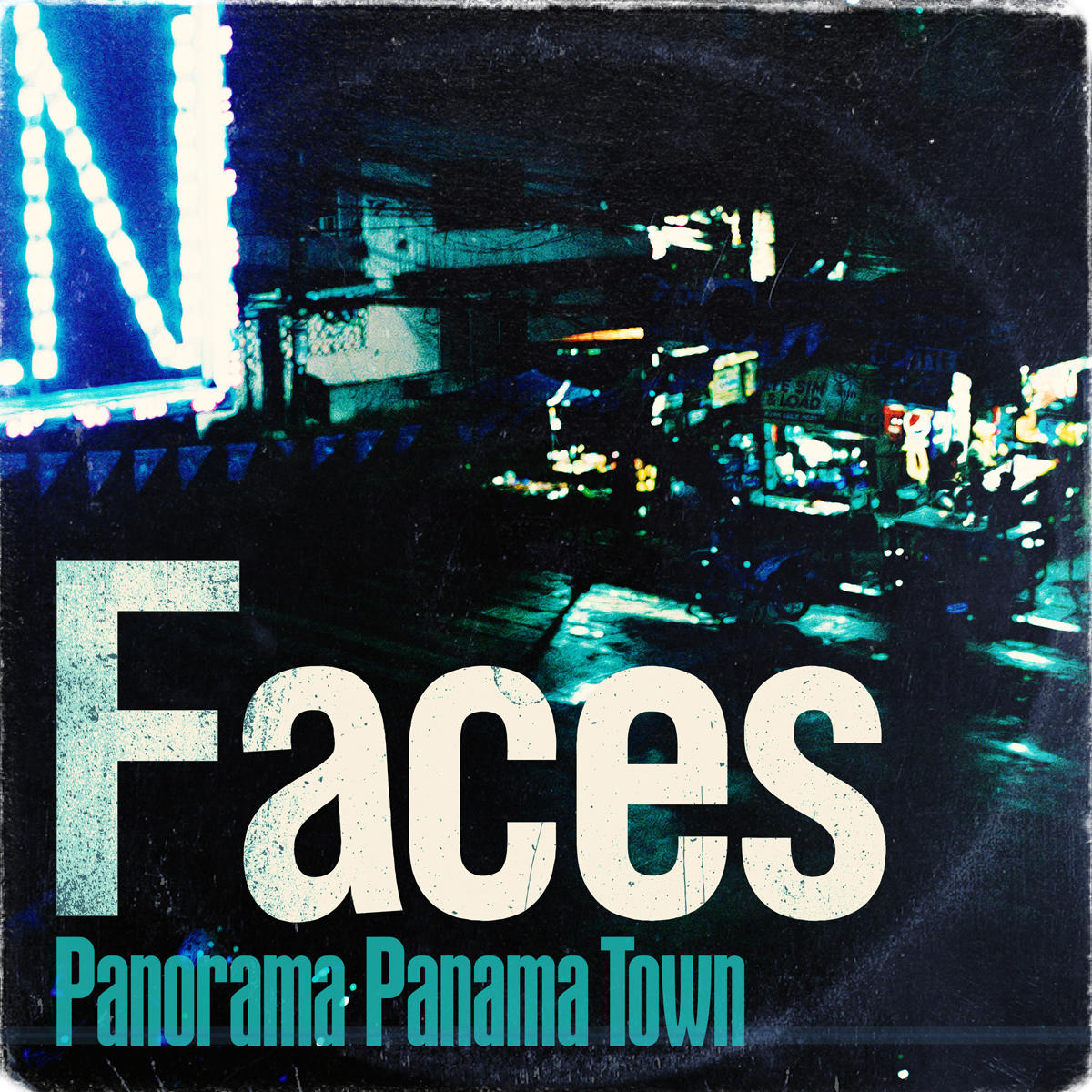
Panorama Panama Town Mini Album『Faces』
2021年11月24日(水)
【通常盤(CDのみ)】AZCS-1103/¥2,200(税別)
Track:
FODドラマ「ギヴン」主題歌「Strange Days」を含む全7曲
購入はこちら
PROFILE

2013年、神戸大学軽音楽部にて結成。バンド名に特に意味はない。叙情的なギターに、
まくし立てるようなボーカルを武器に奔走するオルタナティヴロックバンド。
LINK
オフィシャルサイト@pano_pana
@panoramapanamatown
LINE公式アカウント
通販サイト




