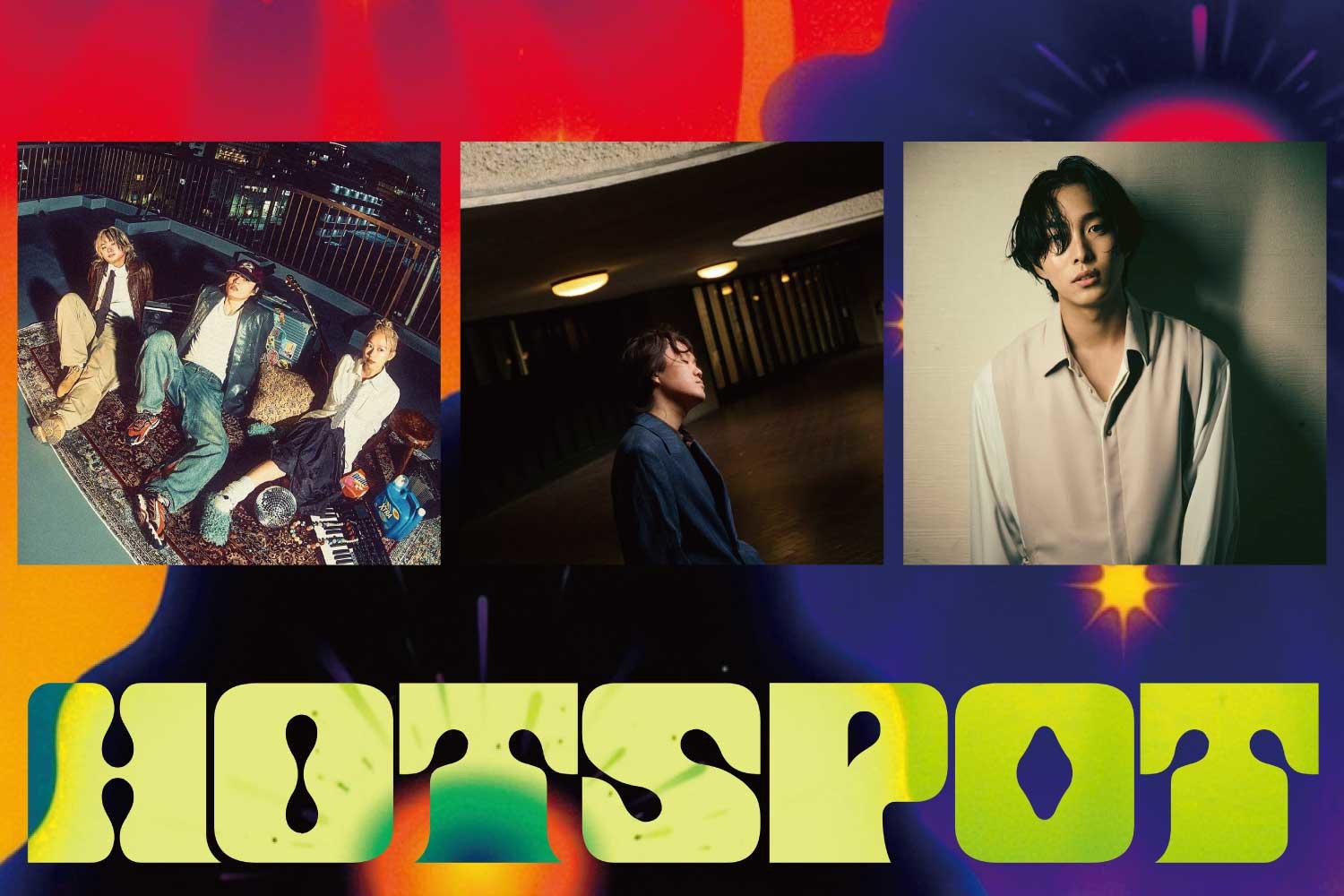Wez Atlas×Yoshi T. サードカルチャーキッズの二人が繋ぐ「東京とNYC」、そして彼らが築く新世代ヒップホップ
INTERVIEW
2025.10.31

業界をリードするマネージメント3社が出資を決意したSURF Musicとは?AI×音楽制作の未来、作家の未来、そして音楽業界の未来について語り合う
SURF Musicは、クリエイターが自身の未発表曲を世界中のエンターテインメント業界のバイヤーに向けて販売できるデジタルマーケットプレイスだ。「Bringing Power Back to Music Creators(音楽のチカラをクリエイターに)」を掲げ、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進している。
先日には、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、株式会社agehasprings、株式会社 レインボーエンタテインメントがビジネスパートナーとして新たにSURF Musicに参加したことも発表された。
2023年のローンチ以来、世界で4万人以上のクリエイターが登録し、国内大手レコード会社が参画するなど急成長を遂げているSURF Music。多くのアーティストを抱えるマネジメント会社にとって、楽曲のデジタルマーケットプレイスが持つ可能性はどのようなものなのだろうか。
このたび、HIP LAND MUSIC代表取締役社長で日本音楽制作者連盟理事長の野村達矢さん、音楽プロデューサーでagehasprings代表の玉井健二さん、RAINBOW ENTERTAINMENT常務取締役の平田幸秀さん、SURF Music のCEOである小堀ケネスさんの4名による座談会が実現した。
SURF Musicについてだけでなく、AIを用いた楽曲制作、ブロックチェーンを用いたコラボレーションツール「FRIENDSHIP. DAO」との連携など、最先端のテクノロジーがもたらす音楽の未来についても語り合ってもらった。

クリエイターと世界中のレコード会社をつなぐプラットフォーム
─まずはSURF Musicを立ち上げた動機について聞かせてください。小堀さんはAIのヒット曲「Story」を手がけるなどすでにJ-POPのプロデューサーとして成功されていたと思いますが、どのような考えがあったんでしょうか。
小堀:SURF Musicは、そもそも自分自身が抱えていた問題を解決しようと構想したものです。もともと僕は音楽プロデューサーとしてマネジメントと契約していたんですが、その頃は同じアーティストの曲を繰り返し作っていて。グローバルに活躍の場を広げるのには限界を感じていました。そこで、クリエイターが自分の未発表曲をアップロードし、世界中のレコード会社がそれを発見して利用できるような、テクノロジーで両者をつなぐプラットフォームを作ればいいんじゃないかと思ったんです。
─SURF Musicはどんな人をユーザーとして想定しているんでしょうか?
小堀:SURF Musicにはクリエイターとバイヤーの二つのユーザーがいます。クリエイターは大御所から新人まで幅広く参加し、それぞれ自分のページに未発表曲を掲載しています。その作風をAIが分析し、近い志向のクリエイター同士がつながることもできます。同時通訳機能によって言葉のバリアを越えてコラボレーションができるようになっています。レコード会社など楽曲を探しているバイヤー側に対してはマジックサーチと銘打ったAIサーチ機能を提供し、新しいクリエイターを発見できるようなプラットフォームになっています。

─玉井さんはいかがでしょうか? クリエイターや作曲家を多く抱えるプロダクションとして、小堀さんがおっしゃったような問題意識をどのように感じていますか?
玉井:いろんな業界に商習慣や不文律があると思いますが、日本では特に作詞作曲の分野に確固たる不文律がある。違う文化圏の人と新しいことをやるハードルが高いんです。例えば、海外のテレビ局のプロデューサーが恋愛リアリティショーのエンディングテーマにぴったりの曲を探していたとします。その曲が新宿の路上で歌っている女子高生の曲だった場合、どうするか。テレビプロデューサーは彼女にどうやってコンタクトするのか? おそらくSNSでしょう。しかしいきなりDMが来ても信用できないし、権利の管理も難しい。誰もがハードルが高いと思い込んでいるわけです。その思い込みをクリアするには、新しい前例を作るしかない。だから僕は僕で似たようなことをやりたいと思っていました。自分なりに準備もしていましたが、小堀さんが先にやった。だから参加するしかないという感じでした。
SURF Musicがもたらす信用担保
─野村さん、平田さんはSURF Musicのビジョンにはどんな印象がありましたか? 出資することを決めた理由についてはどうでしょうか。
野村:今は音楽のビジネススキーム自体が変化してきています。かつてはアーティストがメジャーレーベルと契約し、マネジメントがそれを支える三角関係がありました。しかし今はデジタルツールの進化もあって、レコーディングのコストも大きく下がった。インディペンデントな形態でDIYに活動するアーティストが存在感を高めています。HIP LAND MUSICは、FRIENDSHIP.というアグリゲーションサービス(音源配信代行サービス)を開始したことで、そうしたタイプの独立系アーティストとのつながりができました。そのことは大きな収穫だったんですが、そのようなアーティストたちは海外へ向けてどう発信するのか。作った楽曲をどう見つけてもらえるのか。そこでSURF Musicのプラットフォームが役に立つ。僕らHIP LAND MUSICとしては、SURF Musicを使うことでマネジメントや配信のお手伝いをしているアーティストに対する一つの付加価値を提供できると考えたことが、出資に至った経緯です。SURF Musicを使えば、デモ音源がさまざまな音楽ビジネスに携わる人たちのところに届く可能性が一気に増える。また、アーティスト同士がコライトしたり、コラボレーションしたり、フィーチャリングしたりといった可能性が生まれる。異なる国のクリエイター同士が組むことによって国境を超えたクロスオーバーが生まれる。それがさらなる音楽カルチャーのグローバル化にもつながっていくと考えています。
平田:以前、所属アーティストと楽曲制作をしていた時に、なかなか日本のクリエイターの方は作らないタイプの曲を探してたんです。海外のクリエイターに頼んだ方が良いかなと思ったんですけれど、なかなか思ったようには進まなかった。ちょうどその時SURF Musicのサービスを触らせてもらって「これだ」と一瞬で思いました。アーティストに対して力になれるのではないかと思ったところが大きいです。
─玉井さんはSURF Musicの可能性や強みはどのようなところに感じられましたか?
玉井:一番大きいのは「信用担保」ができるという点です。信頼できる場所で、信頼できる相手と出会える。SURF Musicが信用を担保してくれることで、いろんな交流ができる。まずはこれが大きいです。もう一つは多言語圏に対してアプローチできるという点です。文化圏が違う国は他にもたくさんありますからね。商習慣も権利の考え方も違う。そこにも可能性があると思います。
─小堀さんはいかがでしょうか。SURF Musicの現状についてはどう捉えていますか?
小堀:クリエイターは想定以上の方に参加いただいています。ニーズは確実にあると思いますね。バイヤー側としても、最初は日本のレコード会社に年間契約していただくのが目標だったのですが、YG PLUSさんなど韓国企業との提携も進み、アジアのマーケットに広がっています。今後はさらに機能面を強化し、クリエイターとレーベルのシームレスなコネクションができるようにしていきたいと思っています。
─具体的な取り組み事例についても教えてください。各社でSURF Musicと進めたプロジェクトはありますか?
野村:HIP LAND MUSICとしては、昨年10周年を迎えたThe fin.のデビュー曲「Night Time」のリミックスコンテストをSURF Music上で実施しました。登録クリエイター約4万人に向けてステム(パラデータ)を公開し、解釈の幅が広いリミックスが多く集まりました。どの作品もクオリティが高く、新曲よりもカタログが聴かれるストリーミング時代に非常にフィットした企画でした。いわゆるカタログ活性化という各社のニーズにも合致したアイデアだったと思います。
平田:RAINBOW ENTERTAINMENTでも、所属の新人アーティストREJAYのリミックスコンテストを実施しました。新人ゆえの知名度の課題を懸念していましたが、ふたを開けてみると世界各国から多数質の高い応募が集まり驚かされました。良い発信の場になったと思います。
玉井:agehaspringsとしては、SURF Musicチームと定期的に意見交換を行いながら、当社のコンペ情報の共有やアジアやさらなる多文化圏でのビジネス拡大にむけて、AI楽曲生成サービス「FIMMIGRM(フィミグラム)」をどう活かすかについてもディスカッションしています。
AIと音楽ビジネスの未来像
─玉井さんは早い段階から音楽業界の中での作曲AIへの取り組みを進めてきましたが、そこにはどんな考えがあったんでしょうか。
玉井:作曲AIの可能性を最初に知ったのはずいぶん前です。準備を始めたのはリリースの5、6年前ですね。その時に思ったのは、このままだと技術屋さんが作曲AIを作る未来が訪れるだろうということ。そうではなく、音楽を作るAIは音楽家が作った方がよいというのが自分の考え方でした。そこからいろんな諸先輩方に「AIを作ろうと思うんですが、一緒にやりませんか?」と相談したら、全員に「お前は俺たちの仕事を奪うのか?」と怒られました。でも「違います。逆です」と言い続けてきたんです。
─作曲AIが音楽家の仕事を奪うのではなく増やす、というのは?
玉井:単純明快なことで、例えば、絵の描き方は学校で教わりますよね。写真は誰でも撮れる。IllustratorやPhotoshopを使えばデジタルの画像を作ることもできる。でも、音楽については、楽器を奏でたり歌ったりしたことはあっても、曲をどう作るかを学校では習わないんです。DAWソフトは充実していますが、あれは編曲ソフトであって作曲ソフトではない。メロディをゼロから作ることはできない。でも、作曲AIが当たり前に存在する世の中になれば、誰もがオリジナルの曲を持つようになります。こういう世の中になった時に初めて、本当に素晴らしい作曲家がちゃんと評価される。そういうことを一生懸命話したんですが、誰も協力してくれなかった。そこで、自分でやるしかないということで立ち上げました。そして今もコツコツと作っています。
─現状は他にもさまざまな音楽生成AIが登場し、実際にそれを一般のユーザーが使っています。それを踏まえて、今はどんなことを考えていますか。
玉井:僕らが作っているAIで一番こだわったのが、適法性の確保。音楽家がやっているので、権利に対してのリテラシーがある。他のAIが数秒でどんなに良い曲を作ってくれても、本当にこれを商用利用できるかどうかというのは、担保されていないんです。でも我々はAIが生む曲がイリーガルではないことを担保している。楽曲を似せない技術の特許を取得済みで、この特許がある前提でAIを地道に育てていく。今もそれを続けています。「FIMMIGRM」はB2Bの分野ではかなり実績を積み重ねている。やっていてよかったと思います。

─小堀さん、野村さん、平田さんは、AIの普及によって音楽のあり方やクリエイターのあり方はどのように変わっていくと思いますか?
小堀:これからのクリエイターはAIを一つのツールやインスピレーション源として使っていくと思います。プロンプトで曲をすべて書いてもらうのではなく、自分では思いつかなかったアイディアからクリエイティビティを広げるために使う。AIツールを使いつつ、自分のスキルで曲を完成させる。そういった使い方になっていくのではないかと思います。
平田:AIによって技術が向上することは、やりたいことがあってもクオリティが伴わない若いアーティストにとっては非常にポジティブなことだと思います。ただ、我々としては、アーティストとしての個性や明確なメッセージを持つ人と契約しており、その点は今後ますます重要になっていくと考えています。
野村:生成AIから生まれてくるもの自体を進化させるためには、新しいアイデアでデータベース自体を積み重ねていく必要がある。人間の発想力と人間性が問われる領域は、いつまでもなくならないと思います。その部分で、より新しく、より魅力的な作品を作る挑戦が続くだろうと思いますね。
─これは僕自身の意見ですが、音楽というものは、さまざまなエンターテイメントやコンテンツの中でも、最終的なアウトプットとして身体性が非常に重要な役割を果たす分野であると思います。ボーカロイドやVTuberのカルチャーもありますが、そこでもライブの現場が重視される。そういう観点からも、音楽はAIと人間の相乗効果が期待できる分野の一つなのではないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか?
玉井:おっしゃる通りだと思います。もう少し噛み砕いた言い方をすると、人が好きになるのは人格しかないと思うんですよ。そして人格が伝わるのはストーリーです。だからストーリーに紐づいた曲は売れやすい。それはどういうことかというと、ファンが人格に惚れているということです。だからファンはライブを観て感動してくれるし、そこでグッズも買ってくれるし、チケットをまた取ろうと思ってファンクラブに入ってくれるわけです。僕らが作っているAIはあくまでツールでしかなく、それが人格にはなり得ない。もちろん、AIが人格を感じさせるくらいのストーリーを作り始める可能性は十分にあると思います。未来にはそういうフェーズが訪れるかもしれない。ただ、僕らが人間であることはこの先も変わらない。基本的に人間は人間が好きで、人格にしか思いを寄せない。これは変わらないと思います。だからこれだけAIが絵を描くようになった今も、アートの価値が上がっている。こういう現象はおそらくこの先もっと起こるだろうと捉えています。
ブロックチェーンとクリエイターのエコシステム
─HIP LAND MUSICはブロックチェーンを用いたコラボレーションツールとして「FRIENDSHIP. DAO」を導入しました。ここにはどのようなビジョンがありましたか。
野村:先ほどの話にも重なりますが、音源の聴かれ方がストリーミングに変わり、アーティストやクリエイターを取り巻く経済的な環境、収入のレベルも大きく変わってきました。CDとストリーミングでは音源から得られる収入も違い、これまで音楽業界が作り上げてきたビジネススキーム自体が成立しなくなる部分も出てきている。アウトプットの構造は一気に変わったにもかかわらず、作る側であるアーティストサイドのビジネススキーム自体は変わっていない。そうした状況でアーティストが生計を立てていけるエコシステムをどうやったら作れるのかという発想からDAOに行き着きました。ただ、仮想通貨やステーブルコインがもっと普及していかないと、経済としてのブロックチェーンは成立しない。その進化にはもう少し時間がかかるだろうと思います。「FRIENDSHIP. DAO」に関しては、音楽制作をする人たちのコミュニティをどう作っていくかということが重要だと考えています。
─FRIENDSHIP. DAOが作るクリエイターのコミュニティというのは、SNS的なものというよりも、実際にそこで価値をやり取りしたりシェアできるものを目指しているということでしょうか。
野村:そうですね。経済も伴っているということです。アーティストたちが仮想空間に集まれるようにするためには、何をもって集まるのかというところが重要です。そう考えると、例えばFRIENDSHIP. DAOのサービスの中に、今回のSURF Musicのような、自分が作った音源を世界中のバイヤーの人たちに聴いてもらえるツールがあることは大きい。世界中のアーティストやクリエイターの人たちとどのように結びついて協業できるかは非常に大事です。コミュニティに魅力的な題材がない限りアーティストも動かない。その後押しとなる要素としてSURF Musicのようなサービスは必要だと思っています。

─音楽業界に限らず、クリエイターには基本的に個人事業主が多いと思います。みなそれぞれの領域で活動しながら、人の紹介など、いろんな縁でつながって仕事をしている。そうしたアナログな"縁"をテクノロジーでアップデートする試みが広がっている。そうした見立てについてはどう思いますか?
小堀:FRIENDSHIP. DAOがやろうとしていることはSURF Musicと似ているところもありますし、必要不可欠なものだと思います。音楽業界でも、アナログな紹介で信頼を築き、それが仕事につながるというのがこれまでのやり方だったと思います。でも、これから作ろうとしている新しいエコシステムの中では、クリエイターとバイヤーがつながるだけでなく、ミュージシャンと映像作家など異なる分野のクリエイター同士もつながることができる。かつ、その人が信頼できるかどうかはちゃんとブロックチェーンで可視化される。そこに大きな安心感があると思います。
玉井:未来には新しい形の信頼と信頼の交換が始まっていくと思います。
─クリエイティブビジネスの未来像についても聞かせてください。こうしたサービスが企業や個人に普及した先には、どんなクリエイターのあり方や音楽ビジネスのエコシステムがあり得ると思いますか?
玉井:僕らも一部そうですが、音楽だけでなくエンターテイメント業界は代行業がほとんどです。そうした代行の種類がどんどん細分化されていっているのが今だと思います。きっと、テクノロジーがある面を全て担う未来がくるでしょう。で、さっきの話とつながるんですが、結局そうなるとめちゃくちゃ信頼されているエージェントはAIでなく人間になるんです。そういう人間の価値が上がり、年収も跳ね上がる。そういう近未来が訪れると思います。
─テクノロジーが進化することで人間の価値が上がる、というのは?
玉井:テクノロジーと音楽の相性が良いと僕が思うのは、ミュージシャンやクリエイターは人間関係が苦手な人が多いんですよ。野球をやりたかったけれどチームに入れなかった、みたいな人が多い。人間関係の機微のようなものに上手に対応できなかった、あるいはそれを拒否した人たちが音楽をやっている。そういう人にとって新しいつながり方を提供するという根源的なところに作用するテクノロジーだから、僕らはSurf Musicのサービスと一緒にやろうと思ったんです。そして、僕が首尾一貫して思うのは、選択肢が増えれば増えるほど、人間の魅力がより明らかになるということ。そのことによって、信頼される人間の価値が上がるという未来につながっていくと思っています。
取材・文:柴那典
撮影:斎城弓也
LINK
SURF MusicHIP LAND MUSIC
agehasprings
RAINBOW ENTERTAINMENT