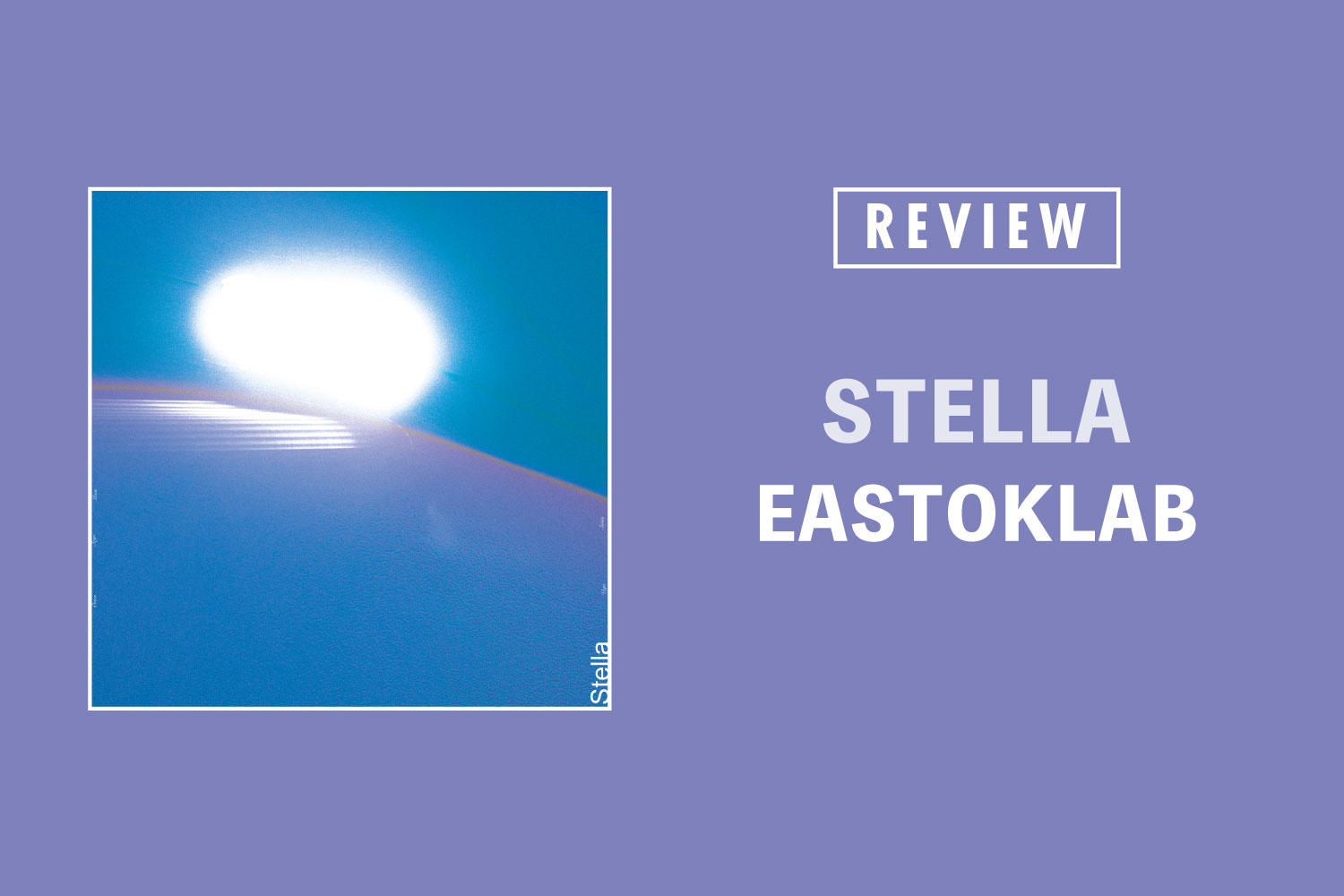- TOPICS
- FEATURE
2025.10.02
若々しくて活力に満ち、ダイナミックでエネルギッシュ。瑞々しくて生気漲り、ヴァイタルでアグレッシヴ。石若駿率いるAnswer to RememberやGentle Forest Jazz Bandでも活躍するトランペッター・佐瀬悠輔のブルーノート東京でのライヴは、そんな形容を並べたくなる熱気に満ちたステージだった。いや、熱気に満ちていたのはステージのみではない。会場であるブルーノート東京もまた、上気した観客で溢れかえっていた。
佐瀬の最新作『BELLOWS』は紛れもない傑作である。シーンと逆行するつくりだと佐瀬自身が言う通り、イントロも1曲も尺が長いし、音圧も1曲を通して一定ではない。そうしたオルタナティヴな提案が含まれているという意味でも、日本のジャズ・シーンに一石を投じるアルバムだったと思う。
ただ、ライヴを観たあとだと、アルバムはオーセンティックに聞こえる。それだけ、ライヴでのアレンジが創意に溢れ、単なるアルバムの再現に終わっていなかったということだろう。佐瀬にはアルバムをただ忠実にライヴで見せても意味がない、という考えがあったのではないだろうか。実際、見る側はどうせなら録音物と毛色の違うものを目撃したいと思うはず。それこそが生の醍醐味なのだから。
というのも、サブスクリプション・サーヴィスでアルバムが気軽に聴けてしまう今、予習として作品を聴いて、それと同じものをライヴで供されて興ざめてしてしまう、という経験が筆者には幾度となくあったからだ。音源には音源ならではの、ライヴにはライヴならではの特質がなければ、現場に足を運ぶ意味が薄れるのではないか。そうしたモヤモヤに佐瀬は答えをくれた。そう、これはアルバムでは聴けなかった演奏だ。そんなことを噛み締めながら約70分に渡るライヴ(ファースト・セット)を観た。

佐瀬はトランペットにディレイをかませ、アルバムでは聴けなかった変調された音色で迫る。ヘヴィ・メタルを通ってきたというのがすぐに分かるギターの小金丸慧眼は1曲目からトバしまくる。無論、アドリブだろうから、アルバムとはまったく異なるフレーズを弾く。更には、エフェクトを駆使して奇矯な音響をアウトプットし、電化マイルスのバンドにおけるピート・コージーやレジー・ルーカスやジョン・スコフィールドのように場を支配する。圧巻だ。小金丸、圧巻である。
King Gnuや君島大空合奏形態でも活躍するエレクトリック・ベースの新井和輝は、硬質な音色が特徴的。彼のベースはアンサンブルという重心を支える背骨のような役割を果たしていた、と言っていいだろう。むろん、ただの縁の下の力持ちではない。長いベースソロも用意されており、野趣に富むプレイを聴かせてくれた。
菊地成孔率いるDC/PRGのメンバーでもある秋元修のドラムはぱっと聴きでは気づかないが、虚心に耳を澄ますと、訛りや揺らぎを含む不可思議なリズムを奏でていると分かる。ひとりポリリズムといった印象もあるし、譜面に起こせない微妙なニュアンスを孕んでおり、実にスリリングだ。ピアノの海堀弘太は曲の冒頭でリリカルでセンチメンタルな旋律を聴かせ、思わず聴き惚れてしまう場面も。かと思うと、曲によってはエレクトリック・ピアノも使用して華やかでカラフルなサウンドも聴かせる。





うたものもある。女性シンガー・ソングライター/トラック・メイカーのermhoiが途中で登場して2曲で歌う。ソロで活躍しながら客演も少なくない彼女は、ケンドリック・ラマー、ロバート・グラスパー、コモンなどの作品でフィーチャーされていた米国のヴォーカリスト、ビラルのような役割を佐瀬のアルバム及びライヴで果たしていた。その伸びやかで透き通った美声は会場を多幸感で満たし、ライヴが一本調子になるのを避けていた。彼女の歌が入ることで全体の構成に起伏と抑揚が生まれていたのだ。

それにしても思うのは、これだけの精鋭を集め、然るべき配置を施した佐瀬の采配の的確さである。そこで連想したのは、電化時代のマイルス・デイヴィスである。同じトランペッターとしては佐瀬と似ても似つかないプレイ・スタイルをもつマイルスだが、マイルスは将来有望な若手を積極的にメンバーに抜擢し、背後から睨みをきかせつつも、自由にスペースを与え、ソロをとらせてきた。
佐瀬はマイルスのように強権的なリーダーではないが、録音やライヴにおいて選び抜いたメンバーは、彼の理想とする音楽を具現化するのみならず、その理想の範疇を飛び超えるような意外性や瞬発力を備えている。彼らを抜擢した佐瀬ですら予想外のプレイを、各メンバーは見せてくれたのではないだろうか。1曲目で小金丸がホットなソロを弾き始めると、佐瀬は笑みを漏らし、「もっとやって」というようなジェスチャーを見せたが、こうした場面が、端的にリーダーとしての資質を物語っているように思う。
佐瀬は30代前半とジャズ界では若手の部類に入るが、メンバーは皆彼と同世代である。もちろん、年齢が低ければいいというわけではない。そうではなく、皆、プレイが若々しいのだ。円熟とか達観といった言葉とは無縁の、野性味あふれる演奏には思わず身体が動くし、全身が総毛立ち、溜飲が下がるような興奮を覚えた。


そして改めて気付かされたのが、佐瀬のコンポーザーとしての才覚である。特にテーマ部分でその傾向は顕現化する。とにかくいいメロディを書く、というのもなんだか芸のない形容だが、そうとしか言いようがない。セロニアス・モンクでもアート・ブレイキーでもソニー・クラークでもリー・モーガンでもいいが、ビバップやファンキー・ジャズのオリジナル曲はテーマが印象的で耳に残る。テーマでその曲を認知/認識/識別していたといってもいい。
それと同じ効果を、佐瀬の書くテーマはもたらしていた。ライヴでテーマが鳴り響くと、「あ、あの曲だ」と耳と身体が即座に反応する。そこから個々のソロに惹きこまれる。いわばテーマが導入として最高の役割を担っていた。むろん、アルバムそのままの始まり方をする曲ばかりではなく、それもそれで刺激的なのだが、テーマが到来すると気分が自然と高揚するのだ。

キャッチーなテーマ、選び抜かれたメンバーによるソロやアドリブ、アルバムとは異なるアレンジと豊かな曲想、起伏と抑揚に富む構成。誇張でも大言でもなく、筆者がジャズに求めるもののほぼすべてが、このライヴにはあった。なお、セットリストは『BELLOWS』中心ながら、前作『#1』からの曲も披露されたのも嬉しいところだ。ちなみに、彼らは今年11月2日に大阪の100BANホールでこのグループとしては初の関西公演を行うとのこと。観に行ける方はぜひ目撃して欲しい。

文:土佐有明
撮影 : 衣斐 誠

佐瀬悠輔「BELLOWS」
2025年7月23日(水)
Format:Digital / CD
Label:FRIENDSHIP.
Track:
1 Reminiscence
2 Off-the-cuff
3 #5
4 Summer's story (feat. ermhoi)
5 Intro
6 Cosmic string
7 Dreamin' (feat. ermhoi)
8 Bellows
試聴はこちら
CD販売サイトはこちら
@yusukesase230
CD販売サイト
佐瀬の最新作『BELLOWS』は紛れもない傑作である。シーンと逆行するつくりだと佐瀬自身が言う通り、イントロも1曲も尺が長いし、音圧も1曲を通して一定ではない。そうしたオルタナティヴな提案が含まれているという意味でも、日本のジャズ・シーンに一石を投じるアルバムだったと思う。
ただ、ライヴを観たあとだと、アルバムはオーセンティックに聞こえる。それだけ、ライヴでのアレンジが創意に溢れ、単なるアルバムの再現に終わっていなかったということだろう。佐瀬にはアルバムをただ忠実にライヴで見せても意味がない、という考えがあったのではないだろうか。実際、見る側はどうせなら録音物と毛色の違うものを目撃したいと思うはず。それこそが生の醍醐味なのだから。
というのも、サブスクリプション・サーヴィスでアルバムが気軽に聴けてしまう今、予習として作品を聴いて、それと同じものをライヴで供されて興ざめてしてしまう、という経験が筆者には幾度となくあったからだ。音源には音源ならではの、ライヴにはライヴならではの特質がなければ、現場に足を運ぶ意味が薄れるのではないか。そうしたモヤモヤに佐瀬は答えをくれた。そう、これはアルバムでは聴けなかった演奏だ。そんなことを噛み締めながら約70分に渡るライヴ(ファースト・セット)を観た。

佐瀬はトランペットにディレイをかませ、アルバムでは聴けなかった変調された音色で迫る。ヘヴィ・メタルを通ってきたというのがすぐに分かるギターの小金丸慧眼は1曲目からトバしまくる。無論、アドリブだろうから、アルバムとはまったく異なるフレーズを弾く。更には、エフェクトを駆使して奇矯な音響をアウトプットし、電化マイルスのバンドにおけるピート・コージーやレジー・ルーカスやジョン・スコフィールドのように場を支配する。圧巻だ。小金丸、圧巻である。
King Gnuや君島大空合奏形態でも活躍するエレクトリック・ベースの新井和輝は、硬質な音色が特徴的。彼のベースはアンサンブルという重心を支える背骨のような役割を果たしていた、と言っていいだろう。むろん、ただの縁の下の力持ちではない。長いベースソロも用意されており、野趣に富むプレイを聴かせてくれた。
菊地成孔率いるDC/PRGのメンバーでもある秋元修のドラムはぱっと聴きでは気づかないが、虚心に耳を澄ますと、訛りや揺らぎを含む不可思議なリズムを奏でていると分かる。ひとりポリリズムといった印象もあるし、譜面に起こせない微妙なニュアンスを孕んでおり、実にスリリングだ。ピアノの海堀弘太は曲の冒頭でリリカルでセンチメンタルな旋律を聴かせ、思わず聴き惚れてしまう場面も。かと思うと、曲によってはエレクトリック・ピアノも使用して華やかでカラフルなサウンドも聴かせる。





うたものもある。女性シンガー・ソングライター/トラック・メイカーのermhoiが途中で登場して2曲で歌う。ソロで活躍しながら客演も少なくない彼女は、ケンドリック・ラマー、ロバート・グラスパー、コモンなどの作品でフィーチャーされていた米国のヴォーカリスト、ビラルのような役割を佐瀬のアルバム及びライヴで果たしていた。その伸びやかで透き通った美声は会場を多幸感で満たし、ライヴが一本調子になるのを避けていた。彼女の歌が入ることで全体の構成に起伏と抑揚が生まれていたのだ。

それにしても思うのは、これだけの精鋭を集め、然るべき配置を施した佐瀬の采配の的確さである。そこで連想したのは、電化時代のマイルス・デイヴィスである。同じトランペッターとしては佐瀬と似ても似つかないプレイ・スタイルをもつマイルスだが、マイルスは将来有望な若手を積極的にメンバーに抜擢し、背後から睨みをきかせつつも、自由にスペースを与え、ソロをとらせてきた。
佐瀬はマイルスのように強権的なリーダーではないが、録音やライヴにおいて選び抜いたメンバーは、彼の理想とする音楽を具現化するのみならず、その理想の範疇を飛び超えるような意外性や瞬発力を備えている。彼らを抜擢した佐瀬ですら予想外のプレイを、各メンバーは見せてくれたのではないだろうか。1曲目で小金丸がホットなソロを弾き始めると、佐瀬は笑みを漏らし、「もっとやって」というようなジェスチャーを見せたが、こうした場面が、端的にリーダーとしての資質を物語っているように思う。
佐瀬は30代前半とジャズ界では若手の部類に入るが、メンバーは皆彼と同世代である。もちろん、年齢が低ければいいというわけではない。そうではなく、皆、プレイが若々しいのだ。円熟とか達観といった言葉とは無縁の、野性味あふれる演奏には思わず身体が動くし、全身が総毛立ち、溜飲が下がるような興奮を覚えた。


そして改めて気付かされたのが、佐瀬のコンポーザーとしての才覚である。特にテーマ部分でその傾向は顕現化する。とにかくいいメロディを書く、というのもなんだか芸のない形容だが、そうとしか言いようがない。セロニアス・モンクでもアート・ブレイキーでもソニー・クラークでもリー・モーガンでもいいが、ビバップやファンキー・ジャズのオリジナル曲はテーマが印象的で耳に残る。テーマでその曲を認知/認識/識別していたといってもいい。
それと同じ効果を、佐瀬の書くテーマはもたらしていた。ライヴでテーマが鳴り響くと、「あ、あの曲だ」と耳と身体が即座に反応する。そこから個々のソロに惹きこまれる。いわばテーマが導入として最高の役割を担っていた。むろん、アルバムそのままの始まり方をする曲ばかりではなく、それもそれで刺激的なのだが、テーマが到来すると気分が自然と高揚するのだ。

キャッチーなテーマ、選び抜かれたメンバーによるソロやアドリブ、アルバムとは異なるアレンジと豊かな曲想、起伏と抑揚に富む構成。誇張でも大言でもなく、筆者がジャズに求めるもののほぼすべてが、このライヴにはあった。なお、セットリストは『BELLOWS』中心ながら、前作『#1』からの曲も披露されたのも嬉しいところだ。ちなみに、彼らは今年11月2日に大阪の100BANホールでこのグループとしては初の関西公演を行うとのこと。観に行ける方はぜひ目撃して欲しい。

文:土佐有明
撮影 : 衣斐 誠
RELEASE INFORMATION

佐瀬悠輔「BELLOWS」
2025年7月23日(水)
Format:Digital / CD
Label:FRIENDSHIP.
Track:
1 Reminiscence
2 Off-the-cuff
3 #5
4 Summer's story (feat. ermhoi)
5 Intro
6 Cosmic string
7 Dreamin' (feat. ermhoi)
8 Bellows
試聴はこちら
CD販売サイトはこちら
LINK
@yusukesase@yusukesase230
CD販売サイト